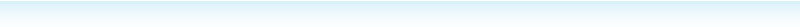
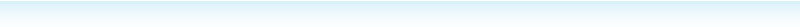
鉄道OB会のあゆみ
鉄道OB会の歴史
| 昭和28年5月 | 「国鉄OB同志会」として発足。 |
|---|---|
| 昭和42年4月 | 「国鉄OB会」に改称。 |
| 昭和62年4月 | 「日本鉄道OB会」に改称。 |
| 平成17年4月 | 「日本鉄道OB会」組織改編。 |
組織改編を行い、6各旅客鉄道株式会社の区域による6つの鉄道OB会と連合会本部で発足。 |
鉄道OB会の胎動
会誕生の気運は、昭和26年10月元東京駅長天野辰太郎氏、元上野駅長富田政助氏等数人の有志が集まって、かつて一緒に仕事をした人達の名簿・会の組織を作り、将来全国的な組織へ広げることを設立の目的としてその動きが始まりました。
さらに、昭和27年6月頃から有志が設立発起人となり、組織の名称を「鉄道OB同志会」とすること、組織活動の目的、活動等について草案づくりと協議を重ね、会の発足に向けて具体的な準備が始まりました。
国鉄OB同志会の発足
昭和28年5月8日会員約200名が参加して、「国鉄OB同志会」の創立総会が開催され、会則の制定、役員の選出及び会長選出等を行ないました。
- 会則「国鉄OB同志会会則」の制定
- 機関紙「国鉄OB同志会会報」の発行
- 会が推薦する運動
ア、会員の消息調査と名簿の整備
イ、会報を発行し、相互の情報交換
ウ、日本国有鉄道に対する協力
エ、会員の地位向上のための文化活動の推進
我が国の鉄道は、創業以来80有余年の歳月を経過して今日に至りました。この間、鉄道は日本国の発展に重要な役割を果たし、我が国の経済と文化の発展に多大の貢献をして参りました。
しかしながら戦時中の酷使により大きな打撃をうけました。戦後漸くにして今日の復旧を見るに至ったのは、諸先輩の不撓不屈の努力の賜物であります。
当時を想起しても、鉄道員は常に誠実であり、あらゆる障害を克服して輸送の使命を果たしたことは、いまだ我々の記録にも新たなところであります。
しかるに鉄道従業員の退職後は、一部の従業員を除き、その消息すら判らなくなってしまうことには、甚だ遺憾とするところであります。
本会は、国鉄の第一線を退いた人々の消息を把握して連絡の緊密を図り、かつ気力を与え、また、退職職員が持つ知識と経験を生かして現職職員に協力する途を拓き、交通文化に資し、以って社会に積極的に貢献しようとするものです。
国鉄OB会の時代
1.組織の見直し、新会則の制定
昭和38年5月の創立10年を経過し、会員数及び支部数は年々目覚しく増加し、さらに、一層飛躍の時に当たり、会の所期の目的達成のためには、これに応ずる組織の整備、運営の合理化が緊要の課題となりました。
組織の全面的改正を検討すべき時期に直面したことから、本部において検討を始め、昭和38年11月の「全国支部長会議」に草案を諮問、検討から3年を経て、昭和41年10月の「全国支部長会議」において、昭和42年4月1日から組織改正に伴う会則改正が実施されることとなり、次のような整備が図られました。
~新会則の概要~
- 会の名称「国鉄OB同志会」を「国鉄OB会」に改称。
- 東京に「中央本部」を設置する。中央本部は、全国共通的な問題について企画し、これを実行するとともに、地方本部の育成並びに地方本部相互間の連絡調整を図る。
- 「地方本部」は、国鉄支社又は管理局の区域ごとに設け、当該地方における組織の中核体として、会の活動及び事業の実施に当たる。
- 支部は、地域活動の実行機関として必要な地域に設け、会員数は100名以上が望ましい。
- 中央本部に理事会を置き、地方本部代表者を理事とする。
- 年1回の「総会」を「全国大会」に改め、全国大会は代議員をもって構成することとし、代議員は地方本部ごとに500名に1名の参加を求めることとする。
2.長寿会員に対する特例措置
昭和47年5月9日、数え80歳に達した会員に対し、終身会費を免除する「長寿会員」制度を実施。
昭和53年度末は、7,918名。昭和54年度末は、8,667名と増加が著しい状況となり、昭和55年5月14日、長寿会員に対する「会費免除」を「会費半額免除」に改正。
平成3年4月1日、会の財政運営に支障を生ずることを懸念し、「会費半額免除」を廃止することにした。ただし、平成3年3月末日までに、既に特典を受けている長寿会員及び長寿の遺族会員については、継続することにした。
3.鉄道開業100年記念
昭和47年10月14日、鉄道開業100年記念式典を本社大会議室において挙行した。同会場に天皇・皇后両陛下がご臨席になられました。
4.国鉄改革に伴うOB会の対応
国鉄分割民営化への移行が実施されるに伴い、昭和61年9月から中央本部に「組織検討委員会」を設けて、協議・検討を開始。
昭和62年2月地方本部長等の関係者を招集し、必要な会則改正案の作成、常任理事会、理事会さらに全国大会に付議等所要手続きを経て、次のとおり昭和62年5月から実施することになった。
- 組織名称は、「国鉄OB会」を「日本鉄道OB会」と改称。
- 国鉄改革に伴い発足するJR各社に対応、年金問題、関係官庁、国会関係等への陳情等が必要と見られ単一組織を維持することとした。
日本鉄道OB会組織改編
平成16年10月20日、臨時理事会を開催し、次のとおり承認されました。
- 日本鉄道OB会は設立から51年を経過し、近年は会員数が減少の傾向にあり、組織の見直しにより活動を活性化させる必要性があること。
- 少子化、高齢化に鑑み、それに対応したきめ細かい活動が求められていること。
- JR発足18年目には、地方組織はそれぞれJR各社に対応する組織を設置するなど、独自の活動が定着しつつあること、以上の状況を踏まえ、「中央本部と地方本部との直結体制」から、JR各社に対応するブロック別に再編成し、それぞれ独立性を持つこととする一方、全国組織は緩やかな「連合会方式」を採用することとなり、実施は平成17年4月1日となりました。
